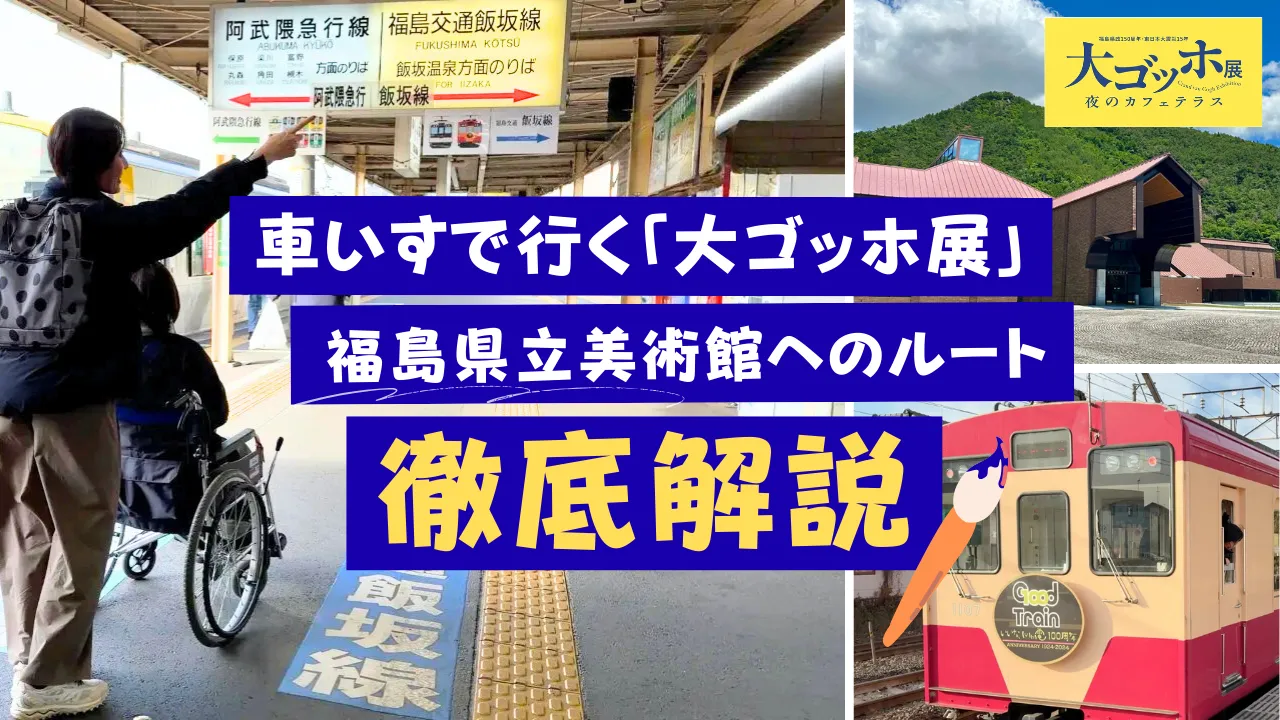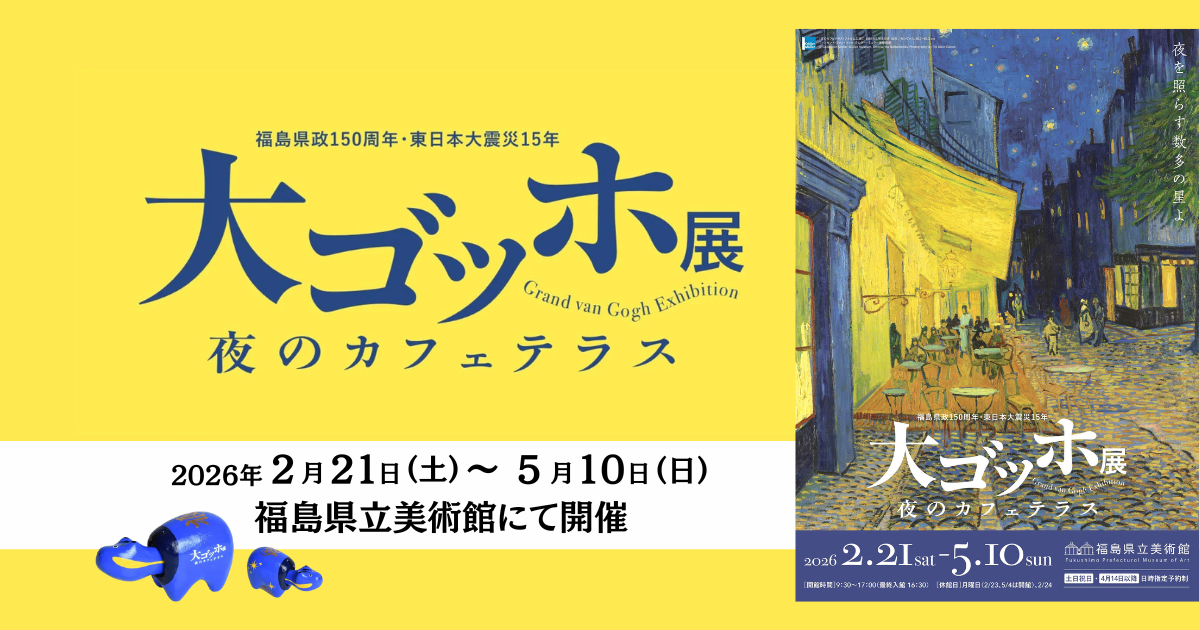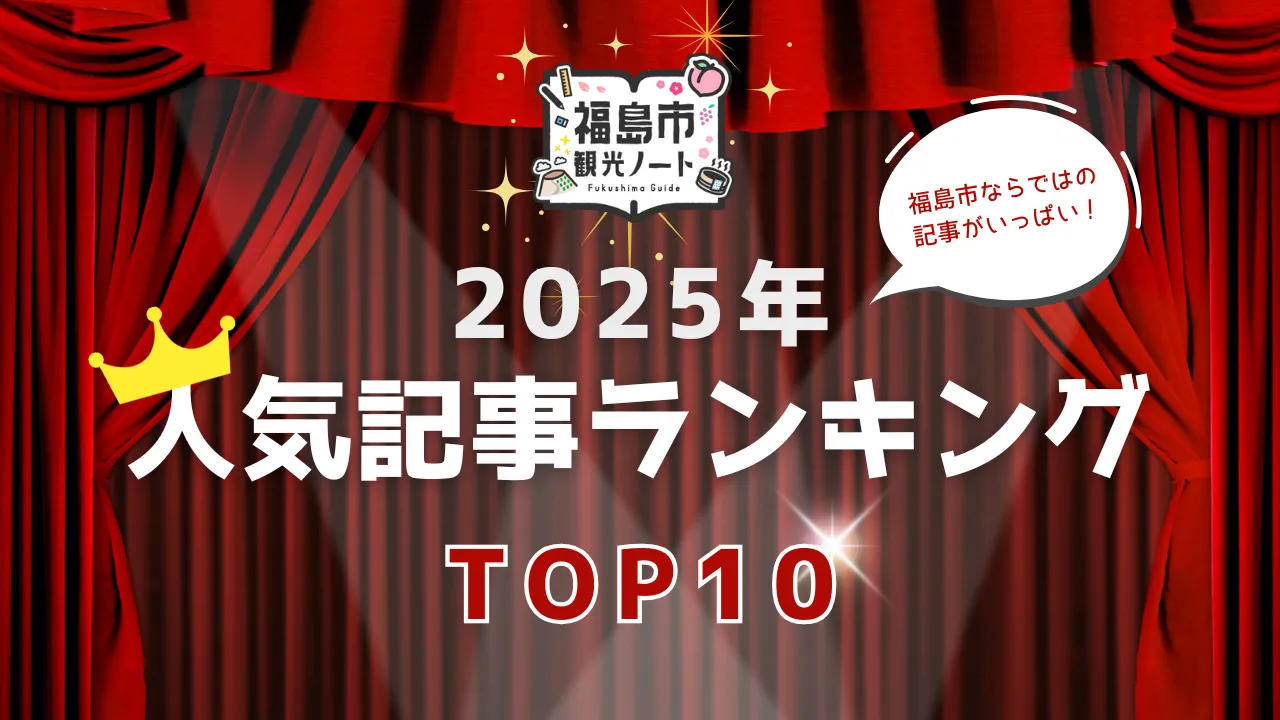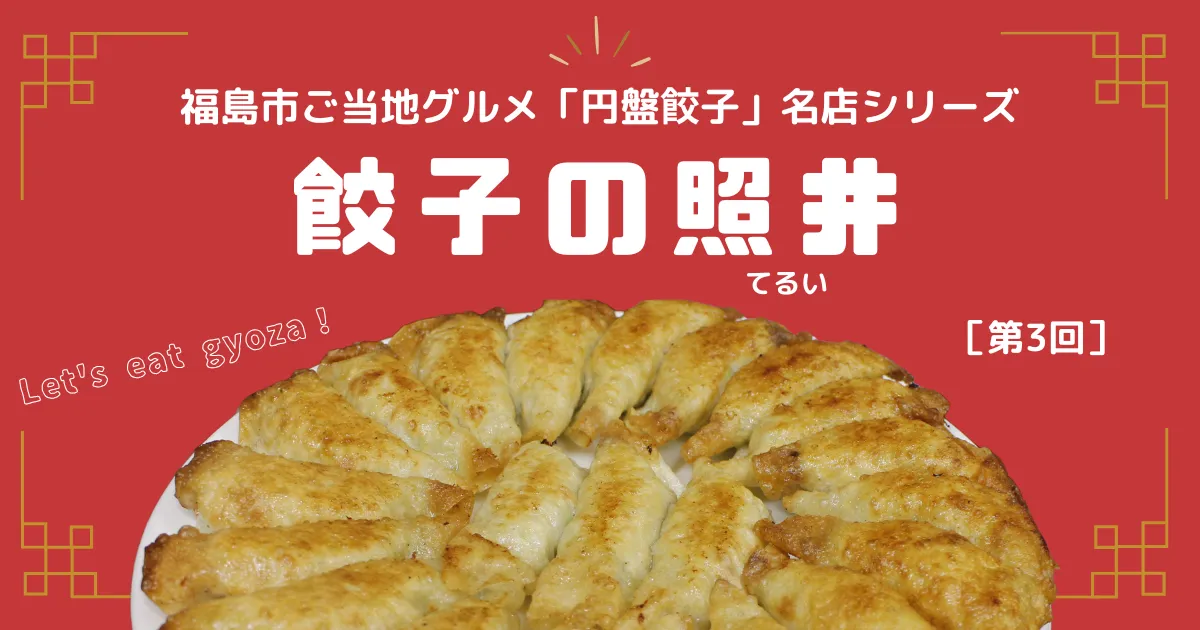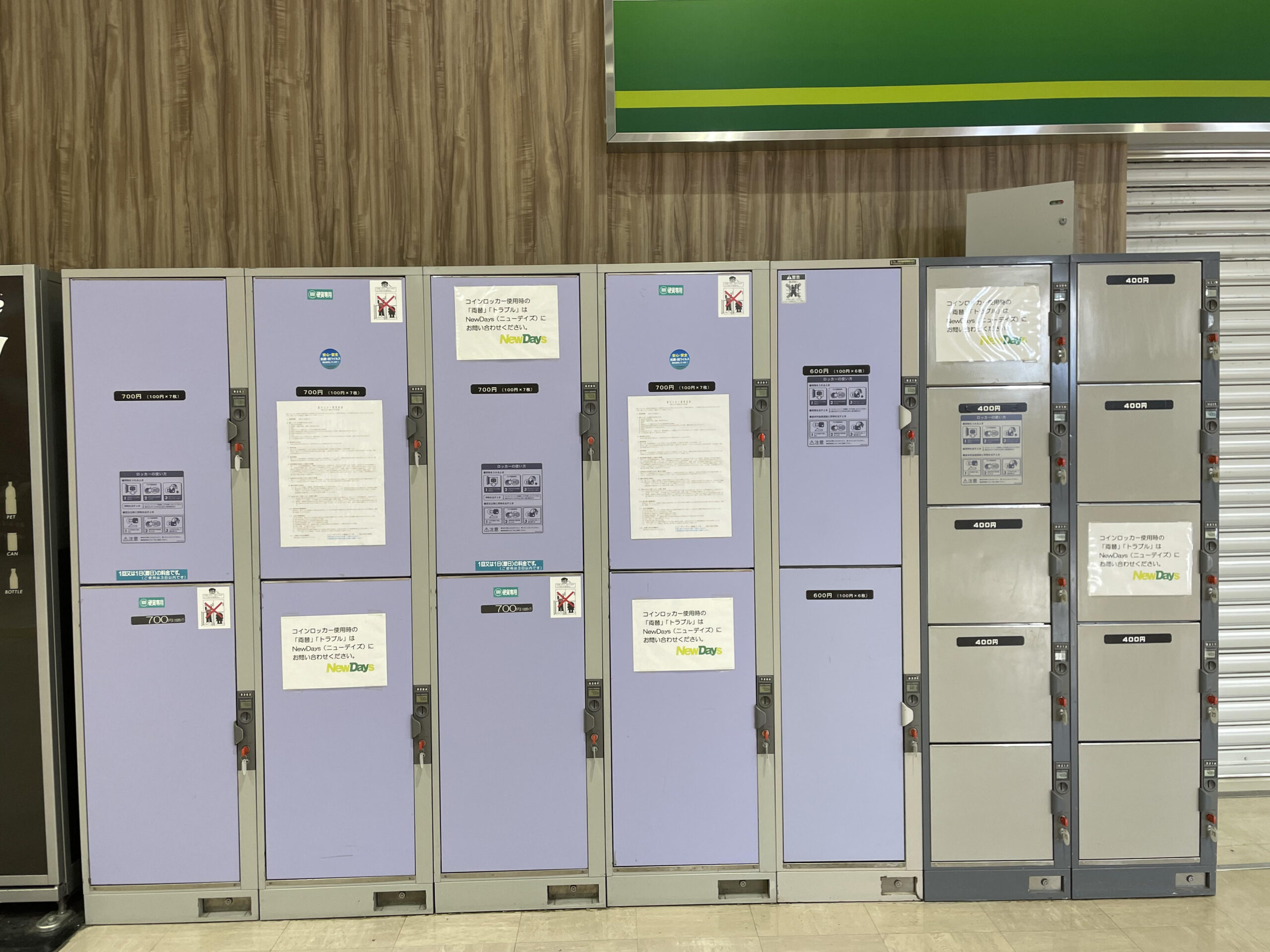掲載日
旅と暮らしの間に漂う、あんな話・こんな話(その3)前よりおいしく感じる訳は
福島市在住9年の観光コンシェルジュ × 取材ライターがお届けするエッセイ
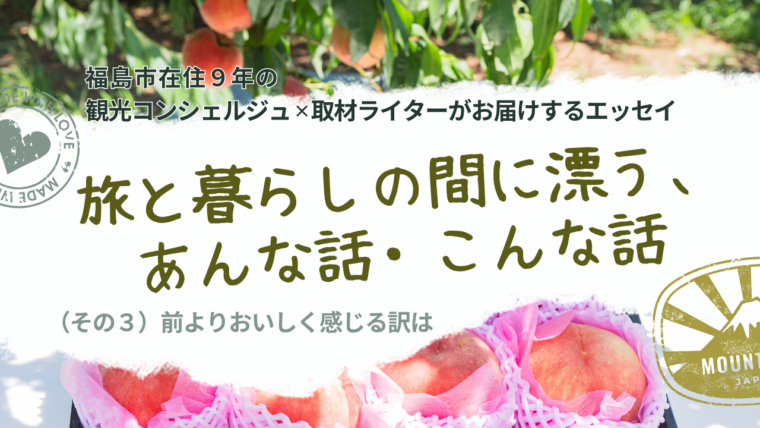
「ちょっと、あなた、そんな爪じゃだめよ。事務所に行って切ってもらいなさい!」
「はい、すみません、すぐ戻ります!」
あいやー、最初から怒られちゃった。
私は低い機械音が響く広い構内を小走りに抜け、隅にある鉄製の階段をカンカンと上がって2階の事務所のドアを叩きました。
「すみません、爪切りって……」
「はい、どうぞ」
こういう不慣れなアルバイトは少なくないのでしょう。職員の方がすぐに引き出しから取り出して渡してくれました。
私とて、桃を触るのだから爪で傷つけてはいけないと思い、前の日にちゃんと短く切ったつもりだったのです。でも、選果場のベテランスタッフのみなさんから見たら、まだ甘かったということ。私はその場で深爪気味に切りそろえ、急いでベルトコンベアの横に戻りました。

福島市の特産、桃の最盛期は7月下旬~8月中旬。その間、市内各地の共同選果場は大忙しで、短期アルバイトが大勢、派遣会社を通じて募集・動員されます。私はこの年、初めて応募し、8月上旬の1週間のみという予定で働き始めたのでした。
短期アルバイトは普通、初心者にとって比較的簡単な箱詰めを担当するらしいのですが、私はどういうわけか最初から、レギュラーの方々に交じって選果のほうに配属されてしまいました。
コンベアに乗ってどんどん流れてくる桃を一つずつ手に取り、色や傷、柔らかさなどで選り分けていくなんて、生まれて初めての作業です。周りのベテランのおばさま方(私も当時すでに十分おばさんでしたが、もっと先輩の方々)から厳しくご指導をいただきつつ、必死で覚えました。
コンベアの速度に遅れまいと、次から次へ桃を見つめて触り続けること一日実働8時間。初日はどうなることかと思いましたが、3日も経つと多少コツがつかめてちょっと余裕が出てきます。
いったい私は1日に何個の桃を選別してるのだろうと思い、試しに数えてみたら、1分間に平均20個。単純計算すれば8時間でなんと9,600個!
1人でそれだけ捌いて、1本のコンベアでは数人ずつ作業していて、そのコンベアが何本もあって、さらにこういう選果場がいくつもあるわけだから……なんという大量の桃が毎日、福島市から全国各地に送られていることか!
いや、それよりもっとびっくりしたことがあります。仕事を終えて家に帰って鏡を見ると、自分が桃に見えたのです! 嘘ではありません。私も目を疑いましたが、本当に、自分の顔や手足の皮膚が桃の肌に見えるのです。
「そうよ、私も最初の頃は、白いタオルがピンクに見えたわ」(先輩のおばさま)
……やっぱりそうでしたか。

4月に咲くサクランボの花

2か月後の姿
私は2017年春にサラリーマンを辞めてフリーランスのライターになったものの、最初のうちはそんなに仕事もないので、いろいろなアルバイトをやりました。
そのほとんどがこうした選果場を含む農業系だったのは、期間限定の募集が多いという理由もありますが、なにより今まで経験したことのない「福島ならではのこと」に挑戦してみたかったからです。
私は、福島に来るまで農業の現場というものをまったく知りませんでした。両親とも祖父母の代から東京だったので、盆暮れに帰省する「いなか」はなく、地方の親戚からお米や野菜が送られてきたなんてこともありません。
もちろん、子どものころブドウ狩りやイチゴ狩りに行った記憶はあります。大人になってからは小旅行で「自家菜園の野菜」が自慢のお宿に泊まり、宿泊者向けの「お野菜収穫体験」なんかをやったこともあります。でもそれらは所詮、おカネを払って楽しむアトラクション。実際の生産の現場とは全然違うはずです。
それで、せっかく福島という農業県に住むことになったのだからと、勤めを辞めた直後は4か月ほどキュウリ農家さんでバイト。翌年からは夏の桃の選果場に加え、春先には桃の摘花、サクランボの授粉、初夏にはサクランボの収穫と箱詰め、ナシの摘果やブドウの摘粒も経験しました。

春から秋までお世話になったキュウリ農家さんにて
たとえ期間限定アルバイトでも、おカネをいただいて仕事として従事すると、頭でわかったつもりだったことが文字通り身体で実感できます。
たとえば桃の摘花。
「え、こんなきれいに咲いてるお花、全部摘んじゃっていいんですか?」
「上を向いて咲いてるのは全部取っちゃいます。ここにこのくらいの実がつくことを想像してみて」
そりゃ、小学校の理科で花が咲いたあとに実がなることは習いました。でも、いま目の前に咲いている可愛らしいピンクの花が、数か月後には店頭に並ぶあの「桃」という果物になるなんて、なんだか魔法のように感じられます。
事実、自然は魔法のようなものかもしれません。どれほど人間ががんばっても、桃の実をつくるのは桃の木であって、人間ではないのです。

桃の花
とはいえ、ただ放っておいたら売り物になるような立派な果物はできません。だから、人間が蕾や花やまだ小さい実を間引く必要があるわけです。ブドウにいたっては、あの一房の中にハサミを入れて小さな粒を一つずつ間引く作業。やってみて気が遠くなりました。
収穫された野菜や果物が、生産者の農場から消費者に届くまでにはこれだけの手数を経るのだということも、選果や箱詰め、出荷の現場を経験して初めてわかったことです。そして、気候変動がどれほど農業生産にダメージを与え得るかということも。
ちなみに、福島のローカル天気予報では、季節外れの高温や低温が予想されるとき、気象予報士が必ず「農産物の管理にご注意ください」とコメントします。「なにそれ? こっちの人はみんな家庭菜園やってるのかしら?」移住したての頃の私はなんと間抜けな想像をしていたことでしょう。
そんなあれこれの体験を経て、私がいま食べる地元の野菜や果物は、前より一層おいしく感じるのでありました。