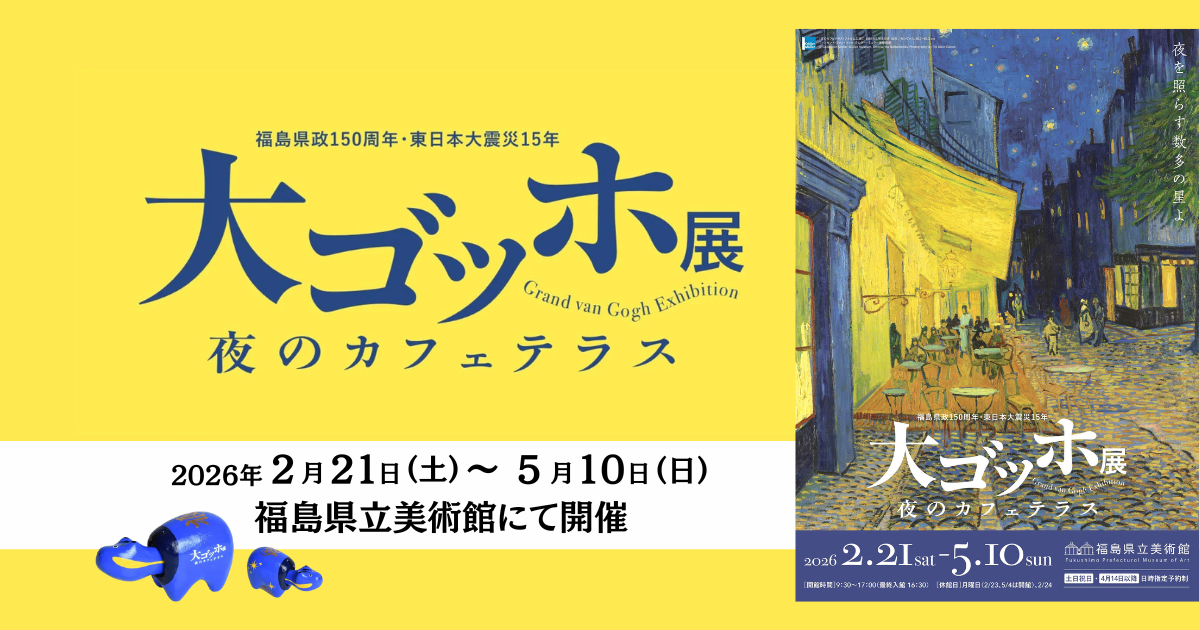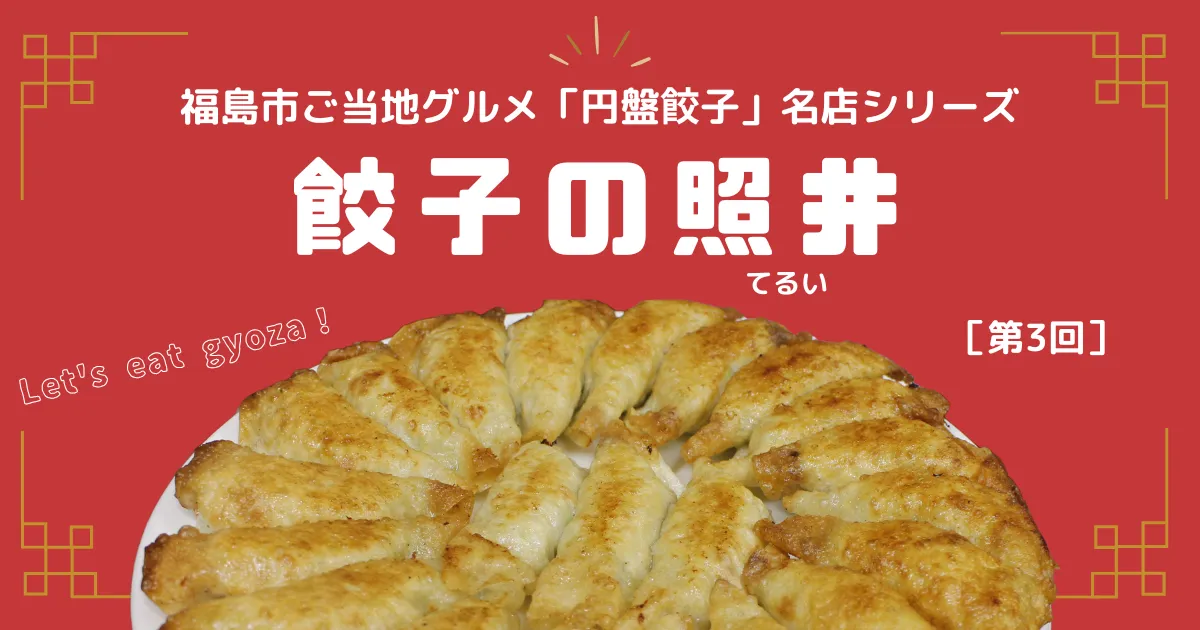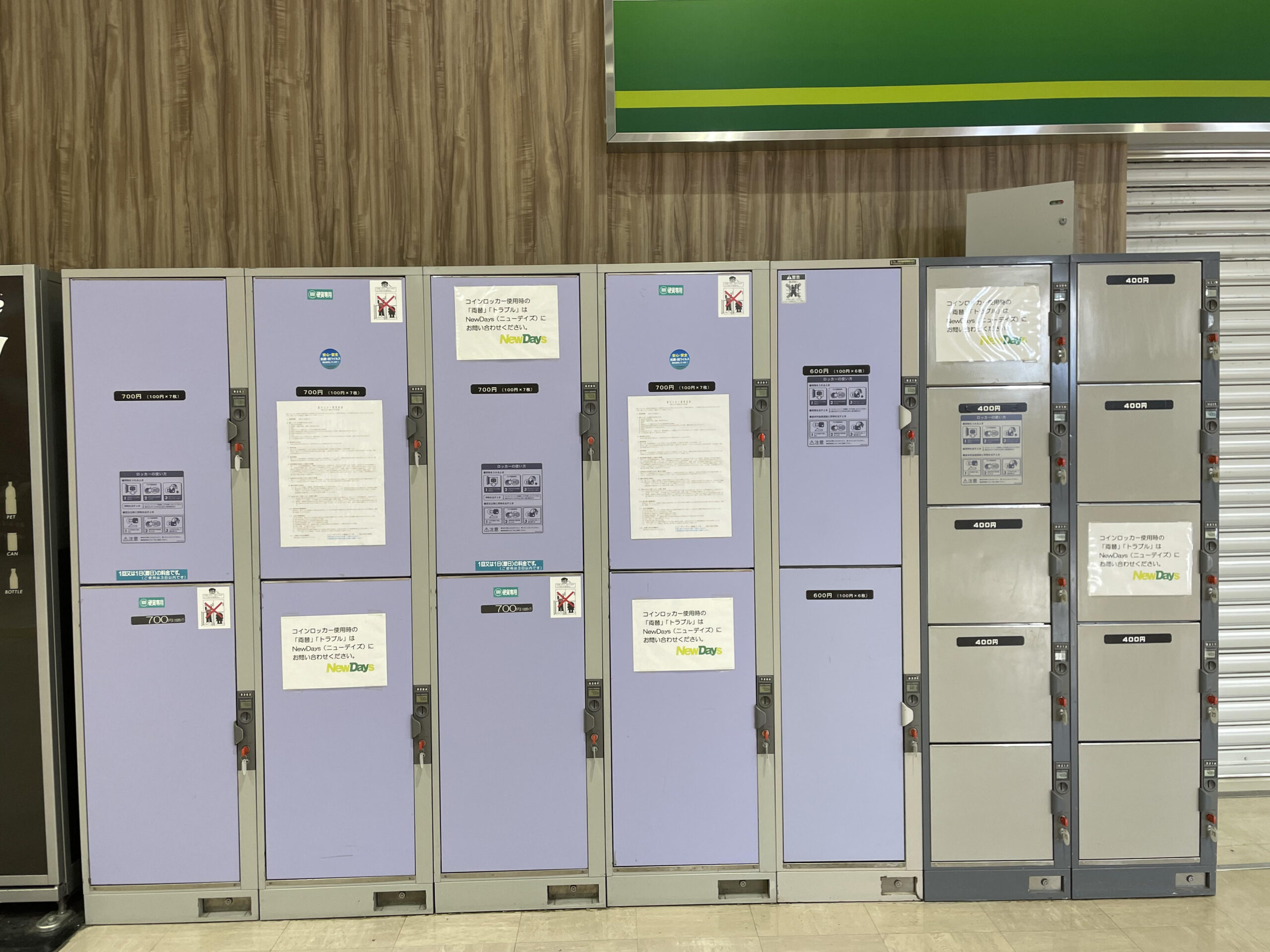掲載日
秋の夜長は福島の美味しいお酒とチーズで乾杯!|ふくしま乳(NEW)発見! 旅するミルク科学 <第4回>
お酒と相性ぴったり「チーズ」にまつわるエトセトラ 福島の観光 × 乳製品 × 科学のコラボ

乳・乳製品のエキスパートである西村順子先生は、現在、日本大学 生物資源科学部 ミルク科学研究室の上席研究員として活躍されています。福島県伊達市出身で、福島大学 食農学類 客員教授も務めており、福島にとてもゆかりのある方です。
福島市で2023年に開かれた「酪農科学シンポジウム」が縁で、福島の旅がもっと楽しくなる「観光 × 乳製品 × 科学」のコラボレーション記事をシリーズで執筆いただいています。
第4回目は「お酒と相性ぴったり『チーズ』にまつわるエトセトラ」です。
チーズの発見と人類発展
ミルヒホルスタイン@藤沢です。すっかり秋めいてきましたが、秋バテなどしていませんか?
秋といえば食欲の秋。秋の夜長に晩酌で一杯という方、かなり多いのではないでしょうか。ちょっと洒落込んでワインにチーズっていう方もおられると思います。
それでは、そのチーズとはいったい何でしょうか? どのようにして作るのでしょうか?
今回は、知っているようで知らない「チーズにまつわる豆知識」をご紹介します。

チーズの歴史は大変古く、紀元前4000年くらいにチグリス・ユーフラテス川の付近で生まれたといわれています。
その頃の人類は、牛や羊、ヤギなどを連れて転々と移動する遊牧生活を送っていました。移動するとき、搾ったミルクを羊の胃袋に入れていたところ、液体だったミルクが固まっており、食べてみたらとても美味! これがチーズの始まりといわれています。
もし固まったミルクを食べようと思わなかったら、チーズはこの世に存在しなかったかもしれませんね。命懸けで食べてくれたご先祖様、本当にありがとう!
その後、チーズはギリシャからヨーロッパへのルートと、シルクロードを通じてアジアへの、2つのルートを辿って世界中に広がっていきました。
ちなみにワイン、パン、ビールも紀元前3000年には製造されていたようで、これらの食品は人類の発展に大きく貢献したといえますね。
ミルクの白さとチーズは大いに関係あり!

先に少し書きましたが、チーズはミルクが固まってできたものです。ミルクが固まることを「凝乳」といいます。とても簡単に平たくいえば、ミルクの白い成分をぎゅっと固めたものなんですよね。
ミルクにはカゼインというタンパク質と乳脂肪が球状で存在していて、光を乱反射するために白く見えるのです。
このうちのカゼインには、球状の外側に水になじみやすい成分が存在しているのですが、仔牛や仔羊の胃にはこの物質を分解する酵素があって、水になじみやすい成分が切り取られ、なじみにくい成分だけが集まって「凝乳」するのです。
実際にチーズを製造するときには、酵素が働きやすいように乳酸菌を加えて少し酸性にして、また凝乳を促す溶液も入れます。
出来上がったときのチーズの重さは、最初に用意したミルクの約10%。つまり、90%は製造工程中に捨ててしまうことになるのですが、とはいえミルクの成分ですから、栄養をたっぷり含んでいます。
チーズにならなかったミルクは、肥料として作物栽培に活用したり、家畜の餌に混ぜるなどして使っていますが、そのまま環境に放出してしまうと環境汚染のもとになってしまいます。私たちの食卓に活用してもらうのが、それが一番なのです。
何かいいアイデアがあったら教えてくださいね!
チーズの種類について

チーズの種類は、ナチュラルチーズとプロセスチーズの大きく2つに分けられます。
ナチュラルチーズ
ナチュラルチーズとは、ミルクに乳酸菌を加えて酵素で凝乳させ、熟成させたものです。水分量と熟成期間の違いによって、フレッシュタイプ、ソフトタイプ、セミハードタイプ、ハードタイプの4つに分けられます。
フレッシュタイプは熟成させないチーズのことで、カッテージチーズやクリームチーズ、モッツァレラチーズ、ストリングチーズ(さけるチーズ)などが挙げられます。爽やかな風味と軽い口触りが特徴なので、おつまみというよりは、料理やお菓子作りの一部に使われる方が多いです。
ソフトタイプのチーズは、加熱や圧搾をせず、短時間の熟成で製造するチーズのことをいいます。このタイプには、カマンベールチーズやブリー、さらには青カビチーズ類も含まれます。
ハード・セミハードタイプのチーズは、加熱圧搾して、水分含量が38%以下のものをハードタイプ、38〜45%のものをセミハードチーズと呼んでいます。ハードタイプには、パルミジャーノ・レッジャーノ、エメンタール、エダムなどがあり、セミハードタイプにはゴーダやラクレットなどがあります。
プロセスチーズ
一方、プロセスチーズは、ナチュラルチーズを細砕して加熱溶解し、乳化剤を入れて成型したものです。加熱してあるため風味が一定しているのが特徴で、みなさんがよく口にしているチーズかと思います。
お酒とチーズの組み合わせ

ワインとチーズ
お酒とチーズの組み合わせというと、パッと浮かんでくるのは、赤ワインと青カビチーズですね。クセのある食べ物が好みの人の定番です。青カビチーズは、ロックフォール、スチルトン、ゴルゴンゾーラが代表的です。
食べる前にカットしておき、少しアンモニアを飛ばしておくと食べやすくなります。
つまみにするチーズは、30〜15分くらい前に冷蔵庫から出しておき、少し常温に置いておくと風味が増して、よりお酒とマッチするようですよ。お試しあれ!
日本酒とチーズ
実は、日本酒にチーズも結構合います。日本酒に、白カビチーズのカマンベールにわさびをつけたり、みそ漬けにしたチーズを合わせたり。クセのある青カビチーズのゴルゴンゾーラも合いますよ。
日本酒の味わい(爽酒・薫酒・醇酒・熟酒)別に良い相性を挙げると、すっきりした味わいの「爽酒」にはモッツァレラなどフレッシュタイプのチーズ、フルーティーな香りの「薫酒」にはカマンベール、米の旨味やコクを感じる「醇酒」にはブリーやゴーダ、古酒などの「熟酒」にはクセのあるゴルゴンゾーラやブルーチーズなどが合うといわれているようです。
今年ももうしばらくすると、新酒の仕込みの時期になります。福島といえば日本酒、今年5月の全国新酒鑑評会でも金賞受賞数日本一に輝いています。多くの福島の日本酒の中から自分に合う日本酒を見つけ、そのつまみにどのチーズが合うのか、探してみるのも一興だと思います。
福島市あづま山麓エリアの多彩なお酒を楽しんで!
福島市のあづま山麓エリアには、日本酒、ビール、ワイン、どぶろくなど、多様な酒を醸造する5つの蔵元が集結しています。
酒造りの方針や伝統を守りながら酒蔵のブランド品質を維持し、志を持って酒類を製造・販売する“造り手”である5人の『蔵元』たちが、自信を持っておすすめする福島市のお酒をお楽しみください。